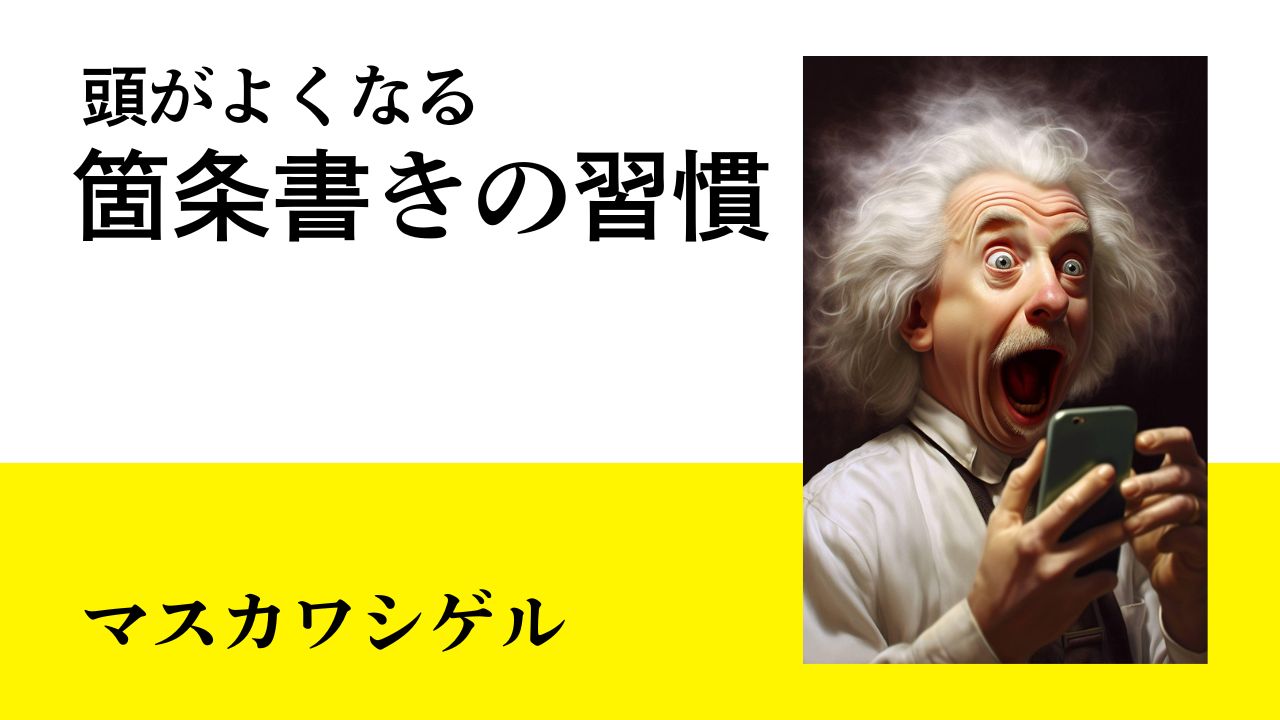基本情報
【書籍情報】
| 書名 | 頭がよくなる箇条書きの習慣 |
| 著者 | マスカワシゲル |
| 出版社 | WAVE出版 |
| 発売日 | 2024年10月 |
| 価格 | 1,980円(税込) |
【目次】
はじめに──箇条書きを制する者はビジネスを制する
序章 仕事がデキる人はみんな箇条書きをしている
第1章 ステップ① 箇条書きを羅列する
第2章 ステップ② 箇条書きをグループに分ける
第3章 ステップ③ 論理ピラミッドを作る
第4章 ステップ④ MECEとメインメッセージを確認する
第5章 ステップ⑤ 要約して文章化する
第6章 MECEに分ける練習
第7章 論理ピラミッドを作る練習
第8章 ビジネスシーンでの活用──報告書、議事録、企画書の作成
おわりに
おすすめのポイント
【おすすめ度】
★☆☆☆☆(1/5)
箇条書きを素材としてビジネス文章を作る方法に興味があればありかも
1.本書の主題は「要約(文章作成)」であって「箇条書き」ではない
2.箇条書きをわざわざ要約文章にする目的・目標が分かりにくい
3.紹介されている箇条書き自体が複雑で分かりにくい
4.レベルの違う知識が混在していて分かりにくい

こんな人におすすめ!
箇条書きを素材としてビジネス文章を作る方法に興味がある人はまず第8章を見て判断してください。
「第8章 ビジネスシーンでの活用──報告書、議事録、企画書の作成」が本題です。



箇条書きそのものを勉強したい人は杉野幹人さんの『超・箇条書き』をおすすめします。
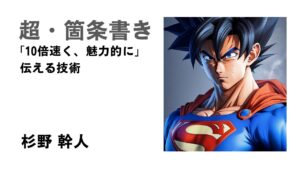
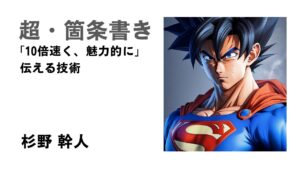
感想
『頭がよくなる箇条書きの習慣』の良いところ
箇条書きを素材としてビジネス文章を作る方法に興味があればありかも
本書の主題は「箇条書き」ではありません。
本書前半は箇条書きを用いて要約文章を作る方法、本書後半ではロジカルシンキングについて説明しています。
そして最終章である第8章にて報告書等の作成方法がまとめられています。
【本書の構成の大枠】
| 前半 | 箇条書きを用いた要約の仕方について |
| 後半 | ロジカルシンキングについて |
| 最終章 | 報告書等のビジネス文章の作り方について |
本書の最終目標は報告書等のビジネス文章を作ることです。
したがって、ビジネス文章の作成術について興味関心がある人には読む価値はあるかもしれません。
ここまで本記事を読んでいただければとっくに分かると思いますが、管理人は本書に対していい印象を持っていません。
その理由を以下の注意点で説明します。
『頭がよくなる箇条書きの習慣』の注意点
前提
私が以前にレビューをした以下の3冊と対比すると本書の問題がよく分かります。
①1分で話せ(伊藤 羊一)
②10倍速く書ける 超スピード文章術(上阪 徹)
③超・箇条書き(杉野 幹人)
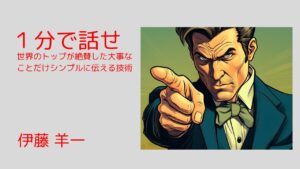
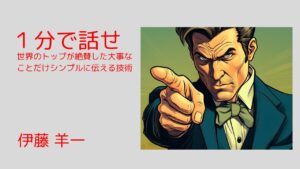


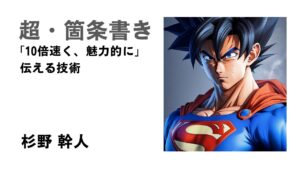
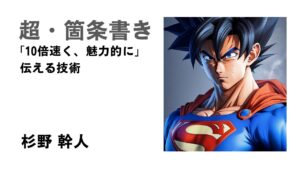
以下の注意点での説明ではこの3冊との対比も行っていきます。
1.本書の主題は「要約(文章作成)」であって「箇条書き」ではない
本書はタイトルに「箇条書き」と入っていますが、主題は要約の作り方であって「箇条書き」ではありません。
箇条書きは要約を作るための手段として使われているだけです。
これが一番の問題点です。
つまり箇条書きを最終的な伝達方法と考えている③超・箇条書きとは書籍の目指すところは異なることになります。
箇条書きを用いて人に情報を伝達したい人からすればタイトルに偽りあり、ということになってしまってもおかしくありません。
タイトルを読めば誰がどう考えても箇条書きをメインに解説してる本に思えますからね。
じゃあ、要約の作り方を解説する本として有益かと問われれば怪しいです。
それが次項以下の話になります。
2.箇条書きをわざわざ要約文章にする目的・目標が分かりにくい
まず、目的と目標について簡潔に説明します。
目的とは、行動の理由です。
目標とは、目的を成就するための具体的な行動や結果になります。
例)
仕事をする目的・目標は?
目的:妻子を養い幸せな家庭を守ること
目標:目的を成就するために必要なお金を稼ぐこと
仕事をする目的、すなわち理由がお金を稼ぐことそのものである人は少ないでしょう。
稼いだお金を使って実現したいことこそが目的になります。
お金を稼ぐという目標は目的との関係では手段の位置づけと言ってもいいかもしれません。
これを本書に当てはめると、本書の目標は第8章にある通り、分かりやすいビジネス文章(報告書・議事録・企画書など)を作成することになります。
まず、この目標が最終章まで読まないと全く分からない点で非常に不親切な本といえます。
前半で長いこと架空の会社のプレスリリースを要約する作業を説明し、後半でロジカルシンキングの話をして、第8章まで読んでなんのために要約の話をしていたのかがようやく分かるわけです。
第8章から読んだ方がいいと言っているのは私だけではないですからね。
このように本の構成が悪い時点で明らかに著者は箇条書きを使いこなせていません。
重要な情報の頭出しのことをガバニングといいます。
ガバニングの技術については③超・箇条書きで説明されています。
さらに言わせてもらえれば、ビジネス文章の作成を「要約」と表現していることにも違和感があります。
もともと、会議の内容などが素材として存在し、その素材から不要な部分をそぎ落として文章にするから「要約」としているのでしょう。
しかし、普通に考えれば単に文章作成術であって「要約」と表現するようなものではありません。
素材から文章を作成する技術については②10倍速く書ける 超スピード文章術で解説されています。
では著者が「要約」の技術を磨いて分かりやすいビジネス文章を作成する目的はなんでしょうか。
この点についてははっきり明言はされていません。
例えば、①1分で話せと③超・箇条書きでは伝達の目的がはっきり示されています。
でも、そうやって人前で何かを伝えるのは手段です。ゴールは先ほど書いたように、何かしらの形で「相手を動かす」ことです。
『1分で話せ』35p
短く、魅力的に伝える箇条書き。そして人を動かす箇条書き。
『超・箇条書き』4ページ
それらを『超・箇条書き』と呼ぶこととする。
ビジネス文章の目的というのは例外なく「相手を動かす」ことになります。
最終的に相手が動いてくれなければいくら分かりやすい文章を作っても意味がありません。
・営業した商品を購入してもらう
・プレゼンした企画に協力してもらう
・上司に自分を出世させてもらう
・就活で自分を採用してもらう
分かりやすい文章そのものには意味がないことは①1分で話せでも明言されています。
ゴールは何か
『1分で話せ』29p
──「理解してもらう」はゴールにならない
本書『頭がよくなる箇条書きの習慣』には要約をする直接の目的は明示されていませんが、推測できる記述は多々あります。
代表的なのは以下の文章でしょう。
この書かれていないことに対する視点が充実すると、さらに要約の価値が上がり、ひいては皆さん自身に対する評価が上がります。
『頭がよくなる箇条書きの習慣』78p
本書では「評価」という言葉が頻繁に出現します。
さらに「評価」以上に出現するのが「上司」というワードです。
要約についても「上司からの指示」「上司に報告」という表現が何度も出てきます。
もちろん「上司からの評価」という表現もあります(37ページ)。
どうも著者であるマスカワシゲルさんの要約の目的は「上司に評価されること」らしいのです。
①1分で話せと③超・箇条書きを読んでいただければ分かるのですが、「上司に評価される」というのはビジネス文章の目的としては微妙なところです。
評価された結果として上司にどう動いてほしいのかまで考えなければ意味がありません。
例えば、企画を通してもらう、企画に協力してもらう、出世させてもらう、給料を上げてもらう、など。
理解されたところで、企画としてはボツ、では意味がないではありませんか。
本書は目的が評価で止まっているせいか、相手の感情に訴えかけるような表現技術の話が一切書かれていません。
情報を分かりやすくまとめることだけを目指しているのです。
要約そのものの目的・目標もはっきりしませんが、何よりも良くないと思ったのは箇条書きをわざわざ要約という文章形式に変換することです。
私が部下に報告を命じた上司であれば部下にこう言います。
「要約とか意味のないことしなくていいから箇条書きのままさっさと出せ」
③超・箇条書きを読めば分かりますが、箇条書きというのは視覚的に理解しやすい優れた伝達方法なんですよ。
箇条書きでまとまっているものをなぜ文章にわざわざ戻す必要があるのですか。
事実、本書『頭がよくなる箇条書きの習慣』では要約文と一緒に箇条書きも提出しろ、と説明されています。
要約が完成したら、報告相手に送るだけです。これにもコツがあります。要約と一緒に箇条書きで作った論理ピラミッドも送るのです。
『頭がよくなる箇条書きの習慣』129p
だったら箇条書きだけでいいのではないでしょうか。
③超・箇条書きなどを参考に分かりやすい箇条書きの書き方を追求する方が合理的です。
ちなみに私が上司から要約を命じられた部下ならばその上司にこう言います。
「自分で原文を読んでください」
実際に管理部門で資料を作る機会は多々あっても「要約しろ」という指示を受けたことは一度もありません。
あえて本書の立場を擁護すれば、要約ではなく報告書や企画書の作成、というのならまだ分かるのですよ。
だったら、「要約」ではなく「箇条書きを用いたビジネス文章作成術」の本として出版すれば良かったのではないかと思います。
③超・箇条書きのような分かりやすい箇条書きの技術の本を読んでいると箇条書きの良さを損なう要約作業には違和感しかありません。
3.紹介されている箇条書き自体が複雑で分かりにくい
以上で説明してきた通り、本書は「箇条書き」を解説した本ではありません。
だからこそやむを得ないのですが、とにかく具体例の箇条書きが読みにくい。
文章作成を前提としているせいか箇条書きの一分が長いです。
加えて、最大で4階層ほどになっており複雑すぎます。
表記方法の混在も見られます。
「・」と「1.」など、記号と番号の箇条書きが一つの例の中に混在しているのです。
本書を「箇条書き」の本として考えるのは無理があります。
4.レベルの違う知識が混在していて分かりにくい
色々な知識を一冊に詰め込み過ぎているというのも本書が分かりにくい理由の一つに感じました。
前半は要約のやり方、後半はロジカルシンキング、最終章はビジネス文書作成術です。
ロジカルシンキングについてもMECEの説明や論理ピラミッドの作り方が解説されており、論理ピラミッドの中ではさらに演繹法と帰納法、統計の話まで出てきてしまっています。
これらはいずれもまともに理解しようとさせれば1冊の本が書けてしまうレベルの知識でしょう。
しかも箇条書きとは直接関係ありません。
著者の初の著書ということで気合が入りすぎてしまったのかもしれませんが、対象となる読者が分からなくなってしまっています。
本書はタイトルに「箇条書き」という言葉が入っています。
③超・箇条書きを読めば分かりますが、箇条書きとは本来情報を分かりやすく整理する技術なんですよ。
あらゆる知識がごっちゃに混ざってしまっていては箇条書きの書籍としての信頼がなくなってしまいます。
おすすめ度★1の理由
以上を読んでいただけらば★1の理由は十分お分かりいただけると思うのですが、ここでまとめます。
私が本書を低評価する理由は大きく2つです。
①「箇条書き」についての本ではない
②要約をする理由がない
①について、タイトルに『頭がよくなる箇条書きの習慣』とあるのですから箇条書きの話をメインでしなければ駄目でしょう。これが一番の問題点です。
②について、内容的にはこれが致命的です。
要は箇条書きを最終の伝達手段と考えていないところがダメなんです。
しつこいですが箇条書きは優れた伝達手段です。
この記事中でも私は何度も箇条書きを使っています。
箇条書きとして情報がまとまっているのであれば要約の形で文章化する必要などありません。
別に本書の文章作成術そのものを否定する気はありませんよ。
箇条書きからビジネス文章を作成する方法としては参考になる可能性もあるとは思っています。
だったら「要約」など経由せずに最初から「箇条書きを用いたビジネス文章作成術」とでもすれば良かったというのは前述した通りです。
しかし、もし文章作成術の本であれば箇条書きそのものについて知りたかった私のような読者は本書を読まなかったでしょう。
タイトルと中身がずれており、かつ中身もいまいちだったため最低評価せざるを得ませんでした。
まとめ
再三申し上げた通り、本書『頭がよくなる箇条書きの習慣』は「箇条書き」そのものについて書かれた本ではありません。
箇条書きそのものについて知りたい人は杉野幹人さんの『超・箇条書き 「10倍速く、魅力的に」伝える技術』をおすすめします。
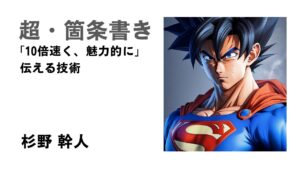
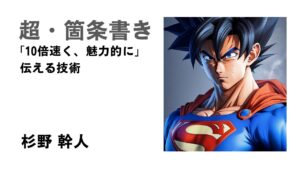
本書『頭がよくなる箇条書きの習慣』は厳密には箇条書きを用いてビジネス文章を作成する方法を解説した本になります。
私はビジネス文章を作成する本については読んだことがありませんので、本書がビジネス文章作成術の本として優れているかどうかの判断はできません。
しかし、全体の構成を考えたときに内容について良い印象を持たなかったのも事実です。
正直に言ってビジネス文章作成術の本としてもあまりおすすめはできないというのが本音になります。