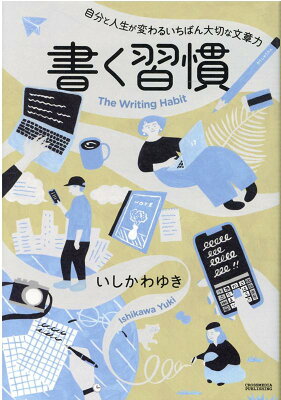基本情報
【書籍情報】
| 書名 | 書く習慣 自分と人生が変わるいちばん大切な文章力 |
| 著者 | いしかわゆき |
| 出版社 | クロスメディア・パブリッシング |
| 発売日 | 2021年9月1日 |
| 価格 | 1,628円(税込) |
| 頁数 | 288ページ |
【目次】
はじめに 人生なんて、「書く」だけで変わる
第1章 言葉と仲良くなれば書けるようになる
第2章 習慣になれば書くのが楽しくなる
第3章 ネタを見つけられると止まらなくなる
第4章 ちゃんと伝わると嬉しくなる
第5章 読まれるともっと好きになる
第6章 「書く」ことが与えてくれるもの
おわりに 「書く」ことで変わるもの、変えちゃいけないもの
「書く習慣」をつくる52のコツまとめ
「書く習慣」1ヶ月チャレンジ
おすすめのポイント
【おすすめ度】
★★★★★(5/5)
1.とにかく書くことに対するハードルが下がるので書けるようになる!
2.小難しいことを考えずに好きなことを書くのが一番!
3.綺麗な文章ではなく、書き手個人の本音が求められているという身も蓋もない事実
4.とはいえ、好き勝手に書くとしても予防線はしっかり示してある
1.書くハードルは下がるが、習慣化の話はあまり書かれていない
2.書く習慣が身に付くとどうお金につながるのか、というプロ視点の話は希薄
3.著者の主観全開な内容は人を選ぶ
4.歩きスマホはアカン
感想
良かった点
1.とにかく書くことに対するハードルが下がるので書けるようになる!
本書を読んで得られる一番のメリットはこれです。
とにかく書くことに対するハードルが、心理的・物理的の両面から格段に下がります。
心理面の話について、ゆきさんは一貫してこう言っています。
もちろん、理由はあるんですよ、かなり説得的な理由が。
それは、
書いている側が「こんなくだらないこと書いてもしょうがないよなぁ」と思ったとしても、読んだ人が感動するなんてことはいくらでもあるわけです。
頭では分かっていてもどうしてもいい文章を書かなくちゃいけないというプレッシャーはあります。
私も今まさにこのレビューを書いていて、もっと気の利いたこと書かなきゃとか思ってるんですよ。
けどそんな躊躇は一切意味がないわけです。
読み手は洗練された文章かどうかなんて気にしてないですからね。
自分の文章に意味づけをするのは読んだ人。
「意味がないかも」と躊躇せず、判断を委ねてみよう。
64p
個人的にはこの書くことに対する心理的ハードルの恐ろしいまでの低下が本書を読んだ一番のメリットでした。
実際、ブログだけでなくXやnote、YouTubeなども内容のクオリティーがいまいちでも発信し続けた者が勝つようなところがあります。
発信を躊躇しない、というのは発信者にとっては最重要要素の一つではないでしょうか。
他方、心理面だけでなく物理面にも触れられています。
とはいえ、物理的な技術についてはおまけ程度ですかね。
要は、書きたくなったらすぐに書ける状況を用意しておけ、ということです。
「秒で書ける状態」にしておくこと。
77p
スマホのホーム画面にメモアプリを置け、といった具体的なアドバイスが複数なされています。
ちなみに、メモをすぐに取れるようにしておく、というのは金持ちが実践している典型的な習慣の一つです。
日本マクドナルド創業者の藤田田さんは『勝てば官軍』をはじめとする著書の中でしつこくメモの重要性を語っています。
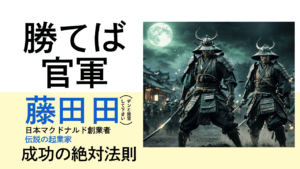
他にもホリエモンこと堀江貴文さんや、『メモの魔力』の前田裕二さんがメモ魔として知られていますね。
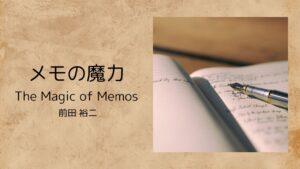
成功者は発信にせよ、自分のためだけのメモにせよ、書くことを躊躇しません。
書くことに対して開き直れる、というのが本書から一番学んだことです。
特にXなんかと相性が良さそうですね。
2.小難しいことを考えずに好きなことを書くのが一番!
セールスライティングとか勉強していると「ジャンル選びが重要だ」なんて話がよく聞こえてきますが、これは眉唾だと思っていました。
本書を読んで確信に変わりました。
どんな文章テクニックをも凌駕する最強のコンテンツ。それは、
133p
「好きなものについて書く」こと。
結局続かないんですよ、好きでも何でもないことは。
実際にネットにおける発信で活躍している人は、儲かるからそれをやっているのではなく好きだからやっている人が多い気がします。
少なくとも私がいつも見ている人はそうです。
ゆきさんはペルソナについても否定的です。
ペルソナというのはネットビジネスにおいて売り手が想定するターゲットの具体像のことです。
40代専業主婦、二児の母、みたいなやつ。
新商品を企画したり、サービスを考えたりするとき、「想定されるターゲットは~」とか「ペルソナ(架空の人物像)は~」と、あらかじめ「どんな人に向けた商品(サービス)か?」を決めることがありますよね。
172p
ときには「年収がいくらで、なにを食べ、どこに住み、どんな暮らしをしているか」など、かなり具体的なイメージを作り込むこともあります。
文章においても「どんな人が読むかを考えて書くことが大切」と言われがち。
でも、そこまで考えているうちに書く気が失せるわ!
めんどくせぇ!!!!
いや、マジでそうなのよ。
知らんがな、って話なのよ。
結局書きたいことはだいたい決まっているし、自分と価値観の近い人が読んでくれるんですよ。
そんでもって価値観の近い人がどういう人なのかなんてはっきり言ってよく分からんのですよ。
特定の商品を売ることだけに特化した文章を書くのでない限り、細かいことを気にするよりもガンガン書いてしまった方が圧倒的に早いです。
特に個人で活動している人はとにかく書くことが最優先ではないでしょうか。
効率的な話を考えるのはその後でしょう。
3.綺麗な文章ではなく、書き手個人の本音が求められているという身も蓋もない事実
これもその通りですね。
みんな書き手の本音が知りたいんですよ。
読まれる文章と、そうでない文章の違いは、
いかに「本音を晒せるか」。これがすべてだといっても過言ではないからです。
216p
例えば、ある商品のレビューとか見たときに当たり障りのない綺麗ごとが書かれていても何の役にも立ちません。
あんた個人はどう思ったの?
これが知りたいんです。
良いことでも悪いことでも。
てことです。
てなわけで、私も今まで以上に好き勝手本音で書きます。
4.とはいえ、好き勝手に書くとしても予防線はしっかり示してある
いくら好き勝手に書くとしても、言っていいことと悪いことはあるわけです。
本書ではちゃんと、やっちゃいけない最低ラインは示してくれています。
端的に言えば、人が傷つくことを書いてはいけないということになります。
不特定多数に向けて文章を書くときは、次の判断基準を大切にしています。
225p
「相手を目の前にしても直接言えるか?」
「その人の人格を否定していないか?」
「わざわざ発信する必要があるか」
何を言っても書いてもいいけど、これだけは守りましょうということですね。
人として最低限のマナーでしょう。
逆に言えば、人に迷惑をかける内容でないのならガンガン書いて公開してしまえばいいということになります。
なにが誰に受けるかなんて発信してみないと分かりませんからね。
気になった点
1.書くハードルは下がるが、習慣化の話はあまり書かれていない
一番気になったのがこれです。
あまり書くことの習慣化そのものについては書かれていない印象を受けました。
確かに書くハードルが下がれば習慣化する確率は上がるでしょう。
しかし、習慣化するための直接的な方法や習慣化されるとどうなるのか、といった記述はほとんどない。
あったとしても私の印象には残っていません。
ブログなどの発信は続けることで爆発的な成果を生むことがあります。
いわゆる複利効果ですね。
長期継続することの効果などを書いてくれると良かったと思います。
2.書く習慣が身に付くとどうお金につながるのか、というプロ視点の話は希薄
多分私のようなブロガーも含めて一番知りたいのは、書き続けると儲かるのどうかということではないでしょうか。
下世話な話ですけど。
本書は書くということについて内容が多岐に渡しすぎており、テーマにまとまりがありません。
・日記
・手帳術
・ブログ
・目標達成術
・ジャーナリング
・スマホのメモ術
こういった書くことに関連する話が、ひたすら出てきます。
確かに書名は『書く習慣』なので、書くことについて書いてあっても間違いではありません。
けど、やっぱり一番知りたいのは書き続けることによって稼げるのかということです。
本書では「書き続けることによって仕事が受注できた」という話も出てくるので、お金を稼ぐことに全く関係ないわけではありません。
しかし記述の量が少ない。
「これだけお金を稼げました!」という話を求めていたので個人的にはやや期待外れではありました。
3.著者の主観全開な内容は人を選ぶ
ちょくちょく本書の文章を引用しているから分かると思いますが、内容は著者であるいしかわゆきさんの主観全開になっています。
ある程度しっかりした文章が書かれている自己啓発本やビジネス書とは違います。
この点、人を選ぶ文体といえるでしょう。
私はそれほど気になりませんでしたが。
4.歩きスマホはアカン
いしかわゆきさん、歩きスマホしてませんかね。
たとえばわたしは、「ゆぴの10分日記」という500~800字程度の記事を書いています。
「帰り道の10分間で書くひとりごとのような日記」と銘打っているとおり、当時の最寄駅から自分の住んでいたマンションまでが自分の歩く速度でちょうど10分程度だったので、毎日その時間を執筆に充てていました。
「毎日更新していてエラいね!」とまわりからは言われていたのですが、本人としては、「だって10分間歩いているあいだ、やることないし・・・・・・」くらいの熱量でした。
歩きスマホはアカンでしょ。
まとめ
色々言いましたが、私自身が本書から受けた影響は大きいです。
「人に迷惑かけるわけじゃないならガンガン発信すればいい」という考えに変わりました。
準備してから書こう、とか考えているようじゃ話にならない。
特にXのようにその場勝負みたいな媒体は思いついたら即ポストでいいんじゃないかとさえ思うようになっています。
実際にポストしてます。
意外と見られているんですよ。
この投稿なんて思いつきでやっただけなのにいいねが複数付くなんて思いもしませんでしたからね。
インプレッション数も3桁行ってるし(私としてすごい方なんですよ!)。
思いついたら即書く習慣がすでに身に付いている人には得るものは少ないかもしれませんが、書くことに躊躇してしまう人には本書はかなりおすすめできます。
はっきり言います、その躊躇は意味ないです。
さっさと書いて公開しちゃってください。
私もそうします。